
執筆者の紹介
運営メンバー:守谷セイ
昔から印刷物を作るのが好きで用紙の種類や色の再現性、加工オプションによって仕上がりが大きく変わることに面白みを感じ、気がつけば自分でも色々なサービスを試したり、比較したりするように。そんな中、「これからネット印刷を利用する人に、最適なサービス選びのポイントを伝えたい」「安心して発注できるような情報をまとめたい」と思い、このサイトを立ち上げました。印刷物って専門的で難しい?なんて言われることもあるけれど、だからこそ、目的に合ったサービスを見つける楽しさもあると思っています。どうぞ、ゆっくり見ていってください!
「印刷物の黒って、K100%でいいんだよね?」「でも、なんだか安っぽい黒になる気が…」「リッチブラックって聞くけど、どうやって作るのが正解なの?」
DTPデザインや印刷データの作成に携わる方なら、一度は「黒」の表現に悩んだ経験があるのではないでしょうか。単純なK100%(スミベタ)では物足りず、かといって闇雲にCMYKの数値を混ぜて「リッチブラック」を作ると、色ムラや裏移りの原因になってしまうことも。せっかくこだわったデザインなのに、黒のせいで台無しになるのは避けたいですよね。
ご安心ください! この記事は、そんなあなたの「黒」に関する悩みをすべて解決し、印刷で差がつく理想的な「黒」を表現するための【完全版】ガイドです。
この記事を読めば、あなたは自信を持って「黒」を使いこなせるようになります。
- なぜK100%だけでは「深みのある黒」が出せないのか? その理由とリッチブラックとの違いが明確になります。
- 推奨されるCMYKの配合数値を含め、IllustratorやPhotoshopでの正確なリッチブラックの作り方をステップバイステップで習得できます。
- 広い面積の黒ベタ印刷で起こりがちな色ムラや裏移りを防ぐための実践的なポイントが手に入ります。
- 「文字や細い線はK100%がいいの? リッチブラックがいいの?」といった、具体的な使い分けの判断基準が分かります。
もう「黒」で失敗する心配はありません。この記事を読み終える頃には、あなたは印刷物の「黒」の表現力を格段に向上させ、見る人を惹きつける深みのあるデザインを自信を持って作り上げられるようになっているでしょう。さあ、最高の「黒」を手に入れるための知識を一緒に学びましょう!
おすすめネット印刷ランキング
印刷の「黒」を理解する:K100%(スミベタ)とリッチブラック
印刷物における「黒」は、実は一種類ではありません。デザイナーが意図する「黒」の表現によって、適切な設定を選び分ける必要があります。特に重要なのが、K100%(スミベタ)とリッチブラックという2つの概念です。これらを正しく理解することが、美しい印刷物を生み出す第一歩となります。
K100%(スミベタ)とは?特徴とメリット・デメリット
K100%とは、CMYKのカラーモードにおいて、Black(K)のインクのみを100%使用する「黒」を指します。一般的に「スミベタ」とも呼ばれ、DTPデータ作成の基本となる黒色です。
特徴:
- C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)のインクを一切含まないため、単色の黒として表現されます。
- 文字や細い線、小さいオブジェクトなどに使用されることが多いです。
メリット:
- 版ズレのリスクが低い: K100%は1色のインクで表現されるため、多色刷りの際に起こりがちな版ズレ(各色の版がわずかにずれる現象)の影響を受けにくいという大きなメリットがあります。文字や細い線がシャープに印刷され、輪郭がぼやけたり、わずかな色のズレが生じたりする心配がありません。
- データがシンプル: 1色のみで構成されるため、データ容量が軽量で処理がシンプルです。
デメリット:
- 深みに欠ける: K100%は、他の色が含まれない単独の黒であるため、広い面積で印刷した場合に、どこか物足りない、薄い、あるいはグレーっぽく見えることがあります。これは、光の吸収率が低いため、見る人によっては「安っぽい黒」と感じられる原因となります。特に、写真やイラストなどの背景で広い面積に使用すると、その印象は顕著になります。
- インクの濃度が低い: 濃度が低いため、紙の質感が透けて見えやすいこともあります。
こうしたK100%の特性を理解しておくことで、どのような場面で使うべきか、あるいは使うべきでないかが明確になります。
リッチブラックとは?深みのある黒を表現する仕組み
K100%の黒が持つ「深みのなさ」を解消するために生まれたのが、リッチブラックです。リッチブラックは、K(黒)のインクだけでなく、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)の他の色インクを少量混ぜ合わせて作られる「黒」のことを指します。
仕組みと特徴:
複数のインクを重ねて刷ることで、単独のK100%では得られない、より重厚感のある、引き締まった「深みのある黒」を表現できます。これは、K以外のインクが光の吸収を助け、視覚的に黒の密度を高めるためです。例えば、C30%・M30%・Y30%・K100%といった形で、K以外の色をプラスするイメージです。
メリット:
- 圧倒的な深みと高級感: 印刷物に高級感や重厚感を与えたい場合に最適です。特に写真の背景や、デザインのキーカラーとして「締まった黒」を使いたい場合に真価を発揮します。
- 色ムラの軽減効果(適切な場合): 広いベタ面でK100%を使用すると、インクの濃度が均一に見えにくく、色ムラが発生しやすいことがあります。リッチブラックは複数のインクを重ねることで、このインクの濃度差を目立ちにくくし、結果的に色ムラを軽減する効果も期待できます。
デメリット:
- 版ズレのリスク: 複数のインクを重ねるため、わずかな版ズレでも色が分離して見えたり、文字のフチにC・M・Yのいずれかの色がはみ出して見えたりする可能性があります。特に細い文字や線、小さいオブジェクトに使う際には注意が必要です。
- 総インク量への注意: 複数の色を混ぜるため、インクの総量が増加します。過剰なインク量は、印刷物の裏移りや乾燥不良、波打ちの原因となるため、適切なCMYKの配合比率を選ぶことが非常に重要です。
リッチブラックは、ただKに他の色を足せば良いというものではありません。その配合比率や使用する場面を誤ると、かえって印刷品質を損ねる原因にもなりかねません。
K100%とリッチブラックの使い分けの基本
ここまでK100%とリッチブラック、それぞれの特徴を見てきましたが、結局のところ、どの「黒」を、どのような場面で使うべきなのでしょうか? 結論から言えば、オブジェクトの種類やデザインの意図によって使い分けるのが正解です。
使い分けの基本的な考え方は以下の通りです。
- K100%(スミベタ)を推奨するケース:
- 小さい文字や細い線: 版ズレによる色ズレを避け、シャープな表現を維持したい場合。特に本文テキストや注意書きなど、視認性が重要な部分。
- QRコードやバーコード: 正確な読み取りを保証するため、単色で構成するのが安全です。
- インク総量を抑えたい場合: コストや乾燥時間を考慮し、極力インクの使用量を減らしたい場合。
- リッチブラックを推奨するケース:
- 広い面積の黒ベタ: ポスターの背景、写真集の地色など、深みと高級感を表現したい場合。
- 写真やイラストの背景: 全体のトーンを引き締め、奥行きを出したい場合。
- タイトルロゴや見出しなど、大きくデザインされた文字: 視覚的なインパクトと重厚感を与えたい場合。ただし、文字の太さやデザインによって版ズレのリスクを考慮する必要があります。
最も重要なのは、「何を表現したいか」と「印刷時のリスクをどこまで許容できるか」のバランスです。次章では、具体的なリッチブラックの作り方や推奨CMYK値、そしてトラブルを避けるための具体的な注意点について詳しく解説していきます。
失敗しない!リッチブラックの作り方と推奨CMYK値
K100%とリッチブラックの特性と使い分けの基本を理解したところで、いよいよ実践編です。ここでは、デザイナーが最も頭を悩ませる「具体的にどのCMYK値でリッチブラックを作ればいいのか?」という疑問に焦点を当て、失敗しないための推奨数値と、Adobe Illustrator・Photoshopでの設定方法を詳しく解説します。
リッチブラックの推奨CMYK数値と設定例
リッチブラックのCMYK配合には様々なバリエーションが存在しますが、闇雲に数値を設定するのは危険です。インクの総量が多すぎると、乾燥不良による裏移りや、用紙の波打ち、色ムラの原因となります。
一般的に、印刷業界で推奨されるリッチブラックのCMYK配合は、総インク量(4色の合計値)が300%前後に収まるように調整するのが理想とされています。これは、多くの印刷機が安定して印刷できる総インク量の上限とされているためです。ただし、用紙の種類や印刷会社の設備によって最適な数値は異なるため、最終的には入稿先の印刷会社の推奨値を優先するようにしましょう。
以下に、代表的なリッチブラックの推奨設定例をいくつかご紹介します。
- 標準的なリッチブラック(迷ったらコレ!):
C30% / M20% / Y20% / K100%
総インク量:170%
解説:わずかにシアンを多めに加えることで、引き締まったシャープな黒を表現できます。多くの印刷会社で推奨される、最も汎用性が高く、トラブルが少ないリッチブラックです。 - クールなリッチブラック(青みがかった黒):
C60% / M40% / Y40% / K100%
総インク量:240%
解説:シアンの比率を高めることで、やや青みがかった、クールでモダンな印象の黒になります。写真の背景などで、引き締まったイメージを出したい場合に効果的です。 - ウォームなリッチブラック(赤みがかった黒):
C30% / M60% / Y60% / K100%
総インク量:250%
解説:マゼンタとイエローの比率を高めることで、温かみのある、深みと落ち着きのある黒になります。夕焼けの風景写真や、重厚な雰囲気を出したいデザインに適しています。 - ディープブラック(最大級の深み):
C50% / M50% / Y50% / K100%
総インク量:250%
解説:各色を均等に配合することで、非常に深みのある漆黒を表現できます。ただし、総インク量が高めになるため、紙の種類によっては裏移りや乾燥不良のリスクが高まる可能性があります。小面積での使用や、事前のテスト印刷が推奨されます。
これらの数値はあくまで目安です。デザインのコンセプトや使用する紙の種類、印刷方法によって最適な「黒」は異なります。可能であれば、少量のサンプル印刷を依頼して、実際に目で見て確認することをおすすめします。
Illustrator/Photoshopでのリッチブラック作成方法
Adobe IllustratorとPhotoshopでリッチブラックを設定する具体的な手順を見ていきましょう。
Adobe Illustratorでの設定方法
- 新規スウォッチの作成:
「ウィンドウ」メニューから「スウォッチ」パネルを開きます。
パネル下部の「新規スウォッチ」アイコン(+マーク)をクリックします。 - スウォッチオプションの設定:
「スウォッチオプション」ダイアログボックスが表示されます。
「カラーモード」が「CMYK」になっていることを確認します。
「カラータイプ」を「特色」ではなく「プロセスカラー」に設定します(印刷でK以外の色を混ぜて表現するため)。
C、M、Y、Kそれぞれのスライダーを動かして、希望するリッチブラックのCMYK値を入力します(例:C30, M20, Y20, K100)。
スウォッチ名に「リッチブラック_C30M20Y20K100」など、分かりやすい名前を付けて「OK」をクリックします。 - オブジェクトへの適用:
作成したリッチブラックスウォッチを、塗りや線に適用したいオブジェクトを選択し、スウォッチパネルからクリックして適用します。
💡ポイント:
作成したリッチブラックスウォッチは、他のドキュメントでも使えるようにライブラリとして保存しておくと便利です(スウォッチパネルメニュー > スウォッチを保存)。
Adobe Photoshopでの設定方法
- カラーピッカーでの設定:
ツールパネルの描画色(または背景色)をクリックして「カラーピッカー」を開きます。 - CMYK値の入力:
カラーピッカーのCMYKセクションに、希望するリッチブラックのCMYK値を直接入力します(例:C30, M20, Y20, K100)。
プレビューで色が確認できるので、意図した黒になっているか確認し、「OK」をクリックします。 - 描画/塗りつぶし:
設定した色で、新規レイヤーの作成やブラシツールでの描画、塗りつぶしなどを行います。
💡ポイント:
Photoshopで作成したリッチブラックは、特に画像データとして書き出す際に重要です。広い面積の背景などに使用する場合は、この方法で設定した黒を適用しましょう。
リッチブラック使用時の注意点(総インク量、色ムラ、裏移りなど)
リッチブラックを効果的に使うためには、以下の点に注意することが不可欠です。
- 総インク量の上限を厳守する:
前述の通り、総インク量は非常に重要です。多くの印刷会社では、総インク量の上限を定めています(通常280%〜320%程度)。これを超えると、インクが乾きにくくなり、裏移り、紙の波打ち、印刷不良の原因となります。必ず入稿先の印刷会社に上限値を確認し、それに従ってCMYK値を設定しましょう。Adobe Acrobat Proの「出力プレビュー」機能で総インク量を確認することもできます。 - 色ムラの発生リスクを理解する:
リッチブラックはK100%よりも色ムラが目立ちにくいとされますが、それでも広い面積のベタ塗りの場合、わずかな色ムラが発生する可能性はゼロではありません。これは、インクの濃度や紙への定着具合、印刷機の特性など様々な要因によって生じます。特に、濃度が高いリッチブラックほど、ムラが見えやすくなる傾向があります。 - 裏移り・ブロッキングに注意する:
インクの総量が多いリッチブラックは、乾燥が不十分な場合、重ねられた次の用紙にインクが付着してしまう「裏移り(ブロッキング)」のリスクが高まります。納品後も重ねて置いておくと、インクが完全に乾ききらず、貼り付いてしまうこともあります。 - 文字や細い線にはK100%を優先する:
リッチブラックは複数のインクを重ねるため、わずかな版ズレで文字や線のフチに色のズレ(見当ズレ)が生じる可能性があります。特にゴシック体などの太い文字は目立ちにくいですが、明朝体のような細い文字や、極細の罫線にはK100%を使用するのが安全です。デザイン上どうしてもリッチブラックの文字を使いたい場合は、フォントサイズを大きくし、太めの書体を選ぶなどの配慮が必要です。 - オーバープリントの設定を理解する:
リッチブラックを含む黒のオブジェクトに、下のオブジェクトが透けて見えないようにするには、通常「オーバープリント」の設定に注意が必要です。DTPソフトで黒のオブジェクトを設定する際、初期設定ではK100%のみがオーバープリントになることが多く、リッチブラックはノックアウト(下の色を白抜きにする)されてしまいます。意図しない結果にならないよう、オブジェクトの属性パネルでオーバープリント設定を確認・調整しましょう。 - 印刷会社との連携が最も重要:
最終的に、最も確実なのは入稿先の印刷会社に推奨されるリッチブラックの数値や設定方法を確認することです。多くの印刷会社は、安定した印刷品質を提供するために、独自の推奨値や注意点をウェブサイトや入稿ガイドで公開しています。疑問があれば、必ず事前に問い合わせるようにしましょう。
これらの注意点を押さえることで、リッチブラックのメリットを最大限に活かしつつ、印刷トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。次章では、さらに一歩進んで、広い面積の黒ベタ印刷で差をつけるための品質向上ポイントを掘り下げていきます。
黒ベタ印刷で差をつける!トラブル回避と品質向上のポイント
ここまでで、リッチブラックの正しい作り方とその注意点について理解を深めていただけたことと思います。しかし、特にポスターやパンフレットの背景、書籍の表紙など、広い面積に「黒ベタ」を使用する場合には、さらに一歩踏み込んだ配慮が必要です。どんなに完璧なCMYK値でリッチブラックを設定しても、印刷工程で起こりがちな「色ムラ」や「網点によるざらつき」といったトラブルは、作品の品質を大きく左右します。このセクションでは、これらの問題を回避し、理想的な黒ベタ印刷を実現するための実践的なポイントを解説します。
広い面積の黒ベタで色ムラが発生する原因
「なぜ、こんなに広い黒ベタの部分だけムラになるんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか? 広い面積の黒ベタ印刷で色ムラが発生する主な原因は、印刷の特性とインクの挙動にあります。
- インクの乾燥速度の不均一さ:
広い面積にインクを均一に塗布することは、非常にデリケートな作業です。特にリッチブラックのように複数のインクを重ねる場合、インクの乾燥速度にわずかな差が生じることがあります。これが、乾燥ムラとなり、肉眼で色ムラとして認識される原因となります。 - 紙の吸湿性・平滑性の影響:
紙の種類によってインクの吸収性が異なります。非塗工紙(コート加工されていない紙)や、表面の平滑性が低い紙では、インクの吸収が不均一になりやすく、ムラが発生しやすくなります。また、紙の繊維の向きや湿度の影響も少なからずあります。 - 印刷機の特性とインクの転移:
印刷機はローラーでインクを紙に転写しますが、その際の圧力やインクの供給量、ローラーの状態などがわずかに変動するだけで、インクの乗り具合に差が出ることがあります。特に高速で大量に印刷する際に、この現象が顕著になりやすいです。 - 網点による視覚的な錯覚:
オフセット印刷は、小さな網点(アミテン)の集合で色を表現します。特にベタ刷りの場合、網点の配列や重なり方がわずかに不均一になることで、人間の目で見てムラやざらつきとして感じられることがあります。これは完全に避けることが難しい現象でもあります。
これらの要因が複合的に絡み合うことで、広い面積の黒ベタに色ムラが発生するのです。
ムラ・ざらつきを防ぐためのデータ作成と印刷のコツ
色ムラやざらつきは完全にゼロにすることは難しいかもしれませんが、データ作成と印刷段階での工夫で、そのリスクを大幅に軽減し、品質を向上させることが可能です。
データ作成のコツ
- 推奨されるリッチブラックの選択:
前章で解説したように、総インク量が過剰にならない範囲で、安定して深い黒を表現できるリッチブラック(例: C30% / M20% / Y20% / K100%)を選びましょう。過度にインクを重ねたリッチブラックは、色ムラのリスクを高めます。 - ノイズやテクスチャの活用:
ベタ一色にせず、ごくわずかなノイズやテクスチャ(木目、かすれ、細かなパターンなど)をオーバーレイや乗算で薄く重ねることで、色ムラを目立ちにくくする効果が期待できます。人間の目は完璧な均一性よりも、わずかな変化がある方がムラを認識しにくい性質を利用したテクニックです。ただし、やりすぎると意図しないデザインになるため、慎重に適用してください。 - グラデーションの活用:
広いベタ面全体を均一な黒にするのではなく、ごくわずかなグラデーション(例えば、中央が少し濃く、端に向かってわずかに薄くなるなど)を加えることで、単調さをなくし、ムラを視覚的にごまかす効果があります。これも非常に繊細な調整が必要な上級テクニックです。 - 背景とオブジェクトの分離:
背景の黒ベタの上に小さな黒のロゴなどを配置する場合、同じリッチブラックを使うのではなく、ロゴはK100%にする、または背景のリッチブラックと異なる配合にすることで、境界線のズレを目立ちにくくできます。
印刷のコツ(印刷会社との連携が重要!)
- 紙の選定:
表面が平滑でインクの吸収が安定しているコート紙やマットコート紙を選ぶことで、ベタ印刷の色ムラを抑えることができます。非塗工紙はインクが沈み込みやすいため、ムラが見えやすい傾向があります。 - 特色(プロセスブラック)の検討:
CMYKの4色で黒を作るリッチブラックとは別に、特色の「プロセスブラック(ディープブラック)」と呼ばれるインクを使用できる場合があります。これは、通常のK100%よりも顔料濃度が高く、1色でより深みのある黒を表現できるため、色ムラのリスクを軽減しつつ、リッチブラックに近い効果を得られる可能性があります。ただし、対応している印刷会社やコストを確認する必要があります。 - 刷り順の調整:
印刷会社は、CMYK各色のインクをどのような順番で刷るかによって、色の乗り方や乾燥に影響が出ることを知っています。黒ベタが重要な印刷物の場合、インクの刷り順を最適化してもらうよう相談することも有効です。 - テスト印刷・本紙校正:
最も確実なのは、本番と同じ紙とインク、印刷機でテスト印刷(本紙校正)を行うことです。特に広い黒ベタが含まれる場合は、画面上では分からないムラや仕上がりを実際に確認できるため、事前に問題を特定し、修正する貴重な機会となります。コストはかかりますが、高い品質を求めるなら強く推奨します。
文字や罫線へのリッチブラック使用の是非
前章でも触れましたが、文字や細い罫線にリッチブラックを使用することは、版ズレのリスクを伴います。結論から言うと、小さい文字や細い罫線にはK100%を使用するのが最も安全で推奨されます。
- K100%推奨の理由:
K100%は1色のインクで構成されているため、多色刷りの際の版ズレが発生しても、文字や線の色自体がズレて見えたり、フチに余計な色が出たりすることがありません。これにより、文字や罫線は常にシャープで読みやすい状態が保たれます。 - リッチブラック使用時の注意点:
どうしてもタイトルロゴや見出しなど、大きく太い文字にリッチブラックの深みを与えたい場合は、以下の点に注意してください。- 文字サイズと太さ: 極端に小さい文字や細い線は避け、ある程度のサイズと太さがある文字に限定しましょう。
- CMYK配合の調整: 総インク量を抑え、Kの割合を高く保ちつつ、他の色の比率を控えめにする(例:C10% / M10% / Y10% / K100%など)ことで、版ズレの影響を軽減できます。
- オーバープリントの設定: 文字が下の色をノックアウト(白抜き)にしないように、オーバープリントが正しく設定されているか確認してください。ただし、これは印刷会社によって推奨が異なる場合があるので、確認が必要です。
- 事前のテスト印刷: リッチブラックの文字を使用する際は、必ずテスト印刷で仕上がりを確認しましょう。
印刷の「黒」は奥が深く、その表現一つで印刷物の印象が大きく変わります。データ作成段階での細やかな配慮と、印刷会社との密なコミュニケーションが、あなたの作品を最高の形で世に送り出す鍵となるでしょう。
よくある質問(FAQ)
リッチブラックのCMYKの割合はどのくらいが良いですか?
リッチブラックのCMYK割合は、インクの総量が300%前後に収まるように調整するのが一般的です。最も汎用性が高く推奨されるのは、C30% / M20% / Y20% / K100%(総インク量170%)です。青みがかった黒にはシアンを、温かみのある黒にはマゼンタやイエローを多めに配合するなど、表現したいイメージに合わせて調整できます。ただし、印刷会社によって推奨値が異なる場合があるので、入稿前に必ず確認しましょう。
リッチブラックとスミベタ(K100%)の違いは何ですか?
スミベタ(K100%)は、Black(K)のインクのみを100%使用した単色の黒です。版ズレのリスクが低い反面、広い面積では薄く感じられたり、安っぽく見えたりすることがあります。一方、リッチブラックはKにC・M・Yのインクを少量混ぜ合わせて作る黒で、より深みがあり重厚感のある表現が可能です。広い面積のベタ塗りに適していますが、総インク量や版ズレに注意が必要です。
リッチブラックを使う際の注意点はありますか?
リッチブラックを使用する際は、以下の点に注意が必要です。
- 総インク量の上限: 印刷会社が定める総インク量(通常280%〜320%程度)を超えないように設定してください。裏移りや乾燥不良の原因になります。
- 版ズレのリスク: 複数のインクを重ねるため、わずかな版ズレでフチに色ズレが生じることがあります。特に小さい文字や細い線にはK100%の使用が推奨されます。
- 色ムラ: 広い面積のベタ塗りでは、インクの乾燥ムラなどにより色ムラが発生する可能性があります。
- 印刷会社との連携: 最適なCMYK値や注意点は印刷会社によって異なるため、事前に推奨値を確認し、必要であればテスト印刷を行いましょう。
黒ベタ印刷で色ムラを防ぐ方法はありますか?
黒ベタ印刷での色ムラは、インクの乾燥速度の不均一さや紙の特性、印刷機の状態など複数の要因で発生します。完全に防ぐことは難しいですが、以下の方法でリスクを軽減し、品質を向上させることができます。
- 推奨リッチブラックの選択: 総インク量が過剰にならない安定したリッチブラックを使用します。
- ノイズやテクスチャの活用: ごくわずかなノイズやテクスチャを重ねることで、視覚的に色ムラを目立ちにくくする効果があります。
- 紙の選定: 表面が平滑なコート紙やマットコート紙を選ぶと、色ムラが目立ちにくくなります。
- テスト印刷・本紙校正: 実際に印刷を行うことで、画面では分からないムラや仕上がりを事前に確認し、調整することができます。
まとめ
本記事では、印刷物の「黒」の表現を大きく左右するK100%(スミベタ)とリッチブラックの特性、そして効果的な使い分けについて詳しく解説しました。深みのある黒を追求するリッチブラックは魅力的ですが、適切なCMYK値の選定と注意点の理解が不可欠です。
ここで、重要なポイントを振り返りましょう。
- K100%は版ズレに強く、細い文字や線に適していますが、深みに欠けます。
- リッチブラックは深みと重厚感をもたらしますが、総インク量や版ズレに注意が必要です。推奨CMYK値はC30% / M20% / Y20% / K100%を参考に、印刷会社に確認しましょう。
- 広い黒ベタでの色ムラやざらつきは、データ作成の工夫(ノイズやテクスチャの活用)や、適切な紙の選定、そして印刷会社との密な連携(テスト印刷など)で改善できます。
印刷物の「黒」は、デザインの印象を決定づける重要な要素です。このガイドで得た知識を活かし、あなたの作品に最高の「黒」を宿らせてください。迷った際は、必ず入稿先の印刷会社に相談し、最適な方法を選ぶことが成功への近道です。今日から、自信を持って理想の「黒」をデザインに落とし込み、見る人を惹きつける印刷物を作り上げましょう!

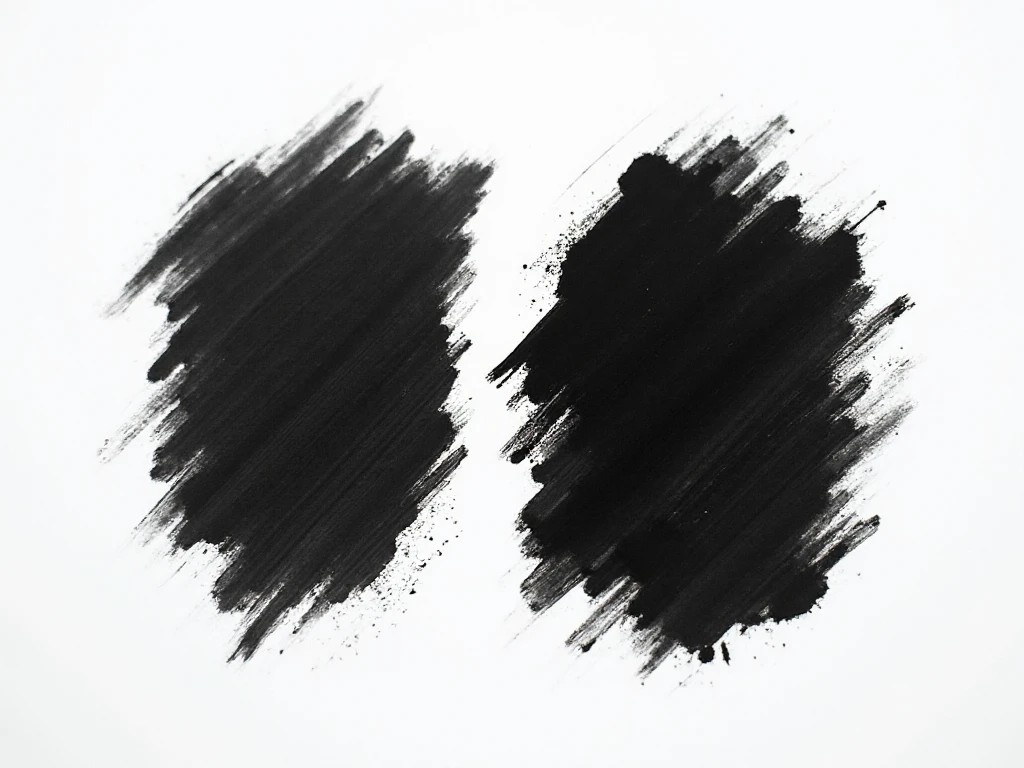




コメント