
執筆者の紹介
運営メンバー:守谷セイ
昔から印刷物を作るのが好きで用紙の種類や色の再現性、加工オプションによって仕上がりが大きく変わることに面白みを感じ、気がつけば自分でも色々なサービスを試したり、比較したりするように。そんな中、「これからネット印刷を利用する人に、最適なサービス選びのポイントを伝えたい」「安心して発注できるような情報をまとめたい」と思い、このサイトを立ち上げました。印刷物って専門的で難しい?なんて言われることもあるけれど、だからこそ、目的に合ったサービスを見つける楽しさもあると思っています。どうぞ、ゆっくり見ていってください!
「楽しみにしていた印刷物が届いたのに、なぜか色が違う…」「文字がかすれている箇所がある…」
苦労して作ったデザインデータを入稿し、ようやく手元に届いた印刷物。しかし、開けてみたら思っていた仕上がりと違ったり、明らかに不良が見つかったりしたら、がっかりしますよね。特に、納期の迫っている重要な印刷物だったり、大量に発注したものだったりすると、焦りや不安も大きくなることでしょう。
もしかしたら、「これって不良品?」「どうやって業者に伝えればいいの?」「交換してもらえるのかな?」と、どう対応すべきか悩んでしまうかもしれません。そんな時でも、落ち着いて適切な対処法を知っていれば、無用なトラブルを避け、スムーズに解決へと導くことができます。
本記事では、【Q&A】印刷物の不良・ミスにどう対応する?原因と解決策を徹底解説と題し、印刷物の不備が見つかった際にあなたが取るべき行動や、今後同様のトラブルを防ぐためのポイントをQ&A形式で分かりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたは以下の疑問を解決し、万が一の印刷トラブルにも冷静かつ適切に対応できるようになるでしょう。
- どんな状態が「印刷不良」と判断されるの?
- 不良品が見つかったら、誰に、どう連絡すればいいの?
- 再印刷や返金など、どのような対応を求められるの?
- 今後、印刷トラブルを未然に防ぐにはどうすればいい?
もう、届いた印刷物の不備に戸惑う必要はありません。正しい知識と対応フローを身につけて、安心して印刷物制作を進めましょう!
おすすめネット印刷ランキング
まずは落ち着いて!印刷物の不備・不良の種類を確認しよう
印刷物が手元に届き、意気揚々と開封した途端に目にした「不備」。思わず慌ててしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて、どのような問題が発生しているのかを具体的に確認することが重要です。一口に「不良品」と言っても、その種類は多岐にわたります。問題を正確に把握することが、その後のスムーズな対応に繋がります。
よくある印刷不良の具体例
印刷物でよく見られる不備や不良には、以下のようなものがあります。ご自身の印刷物がどのタイプに該当するか確認してみましょう。
- 色味の不一致:
- イメージと色が違う:画面で見ていた色と印刷された色が大きく異なる。特に鮮やかな色がくすんでいる、沈んでいるなど。
- 全体的に色が薄い/濃い:指定した色濃度になっていない。
- 色ムラがある:均一であるべき部分に色の濃淡がある。
- 文字・画像の問題:
- 文字のかすれ/にじみ:文字が読みにくい、輪郭がぼやけている。
- 文字・画像の欠け:一部が印刷されていない。
- ゴースト:画像や文字が薄く重複して印刷されている。
- ピンホール/白点:印刷面に小さな白い点や穴が多数見られる。
- モアレ:規則的なパターンが干渉し合い、縞模様や波模様が発生している(特に写真で起こりやすい)。
- フォントの化け:指定したフォントと違うフォントで印刷されている、あるいは文字が記号になっている。
- 断裁・加工の不良:
- 断裁ズレ:仕上がりサイズに対して余白が均等でない、または文字やデザインが途中で切れている。
- 折りのズレ:折り加工の位置がずれている。
- 傷・汚れ:印刷面に傷やインク以外の汚れが付着している。
- 紙のヨレ・シワ:紙が波打っている、または折れ線以外のシワがある。
- 部数不足/過多:注文した部数と届いた部数が異なる。
- その他:
- 紙の種類の間違い:指定した用紙とは異なる紙が使われている。
- 納品物の間違い:全く別の印刷物が届いた。
これらの具体例を参考に、まずは冷静に現状を把握することが肝心です。
不良と判断される基準とは?
「これは不良品だ!」と思っても、全てのケースで印刷会社の責任となるわけではありません。不良と判断される基準は、各印刷会社が定める「免責事項」や「品質基準」に準じます。一般的に、以下のようなケースは不良品として認められやすい傾向にあります。
- 印刷会社の明らかなミス:
- 入稿データ通りに印刷されていない(文字化け、色味の明らかな違い、欠けなど)。
- 断裁や加工のズレが許容範囲を超えている。
- 物理的な損傷や汚れが著しい。
- 指定した用紙と異なる。
- 注文部数と大きく異なる。
- 再印刷や返金対応の対象となりやすいケース:
- 上記のような印刷会社の責任による不備で、印刷物の使用目的に著しい支障が出ると判断される場合。
- 一般的な品質基準から見て明らかに劣る仕上がりの場合。
一方で、以下のような場合は不良品として認められない、または免責となる可能性があります。
- お客様のデータに起因するミス:
- 入稿データそのものが間違っていた(誤字脱字、画像解像度不足、塗り足し不足、RGBデータのCMYK変換による色味変化の許容範囲内など)。
- データに隠れていたレイヤーが印刷されてしまった、非表示にすべきものが表示されてしまった。
- 許容範囲内の仕上がり:
- 多少の断裁ズレ(数ミリ程度のズレは一般的に許容範囲とされることが多い)。
- 画面と印刷物の色味のわずかな違い(RGBとCMYKの色域の違いによるもの)。
- 紙の特性上避けられない現象(紙の伸縮による若干の寸法誤差など)。
- 納期遅延など:
- 印刷品質とは直接関係ないものの、納期に間に合わなかった。ただし、この場合でも印刷会社の責任であれば別途対応されることがあります。
重要なのは、各印刷会社のウェブサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「免責事項」「品質基準」などを確認することです。多くの場合、不良品の定義や対応範囲について明記されています。まずは落ち着いて、届いた印刷物の状態と照らし合わせ、どのような不備が発生しているのか、そしてそれが不良と判断される範疇にあるのかどうかを冷静に判断しましょう。この確認が、次のステップである印刷会社への連絡をスムーズに進めるための鍵となります。
印刷物の不備・不良が見つかった場合の対応フロー
印刷物の不良の種類と、それが不良と判断される基準について理解できましたか?次に、実際に不備が見つかってしまった場合に、どのように印刷会社と連絡を取り、問題を解決へと導くべきか、具体的な対応フローを解説します。適切な手順を踏むことで、スムーズな解決に繋がりやすくなります。
① 不良箇所を明確に記録する
印刷会社に連絡する前に、まずは不良箇所をできるだけ詳細に、客観的に記録しておくことが重要です。これは、状況を正確に伝え、印刷会社が原因を特定し、適切な対応を判断するために不可欠な情報となります。
- 写真や動画を撮る:
- 不良箇所を複数枚の写真で撮影しましょう。全体がわかるもの、特に問題の部分を拡大したものなど、様々な角度から撮ると良いです。
- 色味の問題であれば、可能な限り自然光の下で撮影し、画面の色との比較写真も用意すると伝わりやすくなります。
- 断裁ズレや加工不良の場合は、定規を当てて具体的なズレの寸法がわかるように撮影すると、より客観的な証拠となります。
- 動画で、全体的な状態や特定の不良が連続して発生している様子などを記録するのも有効です。
- 不良品のサンプルを確保する:
- 可能であれば、問題のある印刷物をいくつか手元に残しておきましょう。印刷会社から現物の送付を求められる場合があります。
- 多数の不良品がある場合でも、問題が特に顕著なものを数点ピックアップしておくと良いでしょう。
- 不良の内容を具体的にメモする:
- 「色が変」ではなく、「全体的に赤みが強い」「特定の部分だけ青みがかっていてムラがある」など、具体的に記述しましょう。
- どのページに、どの程度の頻度で、どのような不良が発生しているのか(例:100枚中50枚にこの不良が見られる)など、具体的な状況を記録します。
- 注文番号、商品名、入稿日、納品日など、取引に関する情報も控えておきましょう。
これらの記録は、後々のやり取りにおいて、言った言わないのトラブルを防ぎ、スムーズなコミュニケーションの助けとなります。
② 印刷会社への連絡と状況説明
不良箇所の記録が済んだら、次に印刷会社へ連絡します。迅速な連絡が、問題解決の鍵となります。多くの印刷会社では、不良品に関する問い合わせの窓口や、対応期間が定められていますので、まずはウェブサイトで確認しましょう。
- 連絡手段を確認する:
- 電話、メール、問い合わせフォームなど、印刷会社が推奨する連絡手段を利用しましょう。特に写真やデータを送る必要があるため、メールや問い合わせフォームが適している場合が多いです。
- 伝えるべき内容:
- 注文番号:必須です。
- 氏名・連絡先:担当者名も伝えましょう。
- 不良の具体的な内容:前述の記録に基づき、どのような不備があるのかを簡潔かつ具体的に伝えます。
- 不良の発生枚数・割合:「全枚数」「約半分」「特定の箇所に集中している」など。
- 不良箇所の写真や動画の添付:視覚的な情報があることで、印刷会社も状況を把握しやすくなります。
- 希望する対応:再印刷、返金、一部交換など、現時点で希望する対応を伝えておくと、その後の交渉がスムーズに進みます。
- 連絡はできるだけ早く:
- 商品到着後、すぐに内容を確認し、問題があれば速やかに連絡しましょう。多くの印刷会社では、商品到着から7日以内など、連絡期限を設けています。この期間を過ぎると対応してもらえない可能性があるので注意が必要です。
冷静かつ丁寧に、事実を明確に伝えることが、印刷会社との良好な関係を保ち、解決に導く上で非常に重要です。
③ 再印刷・返金などの対応交渉
印刷会社からの連絡を待ち、対応について交渉を行います。印刷会社は、不良品の状況を確認した上で、再印刷や返金、あるいは割引などの対応策を提案してきます。
- 印刷会社の対応を確認する:
- 印刷会社は、送られた写真や現物を確認し、自社の品質基準に照らし合わせて不良と判断するかどうかを連絡してきます。
- 原因が印刷会社側にあると認められた場合、具体的な対応策が提示されます。
- 再印刷の場合:
- 納期:再印刷にかかる期間を確認し、元の納期に間に合うか、代替案があるかなどを相談しましょう。
- 費用:もちろん、印刷会社の責任による再印刷であれば、追加費用は発生しません。
- 返金の場合:
- 返金額:全額返金か、不良品の割合に応じた一部返金かを確認します。
- 返金時期:いつ頃返金されるのかを確認しておきましょう。
- 一部交換・割引などの場合:
- 不良品が一部のみの場合、その不良品のみを交換するか、全体の料金から割引されるなどの対応が提示されることがあります。
- 提示された内容で納得できるか、ご自身の状況と照らし合わせて判断しましょう。
- 粘り強く交渉する姿勢も大切:
- もし印刷会社の提示する対応に納得がいかない場合は、具体的な理由を述べ、ご自身の希望を再度伝えましょう。ただし、感情的にならず、あくまで冷静に話し合いを進めることが重要です。
- 契約内容や利用規約を再度確認し、自身の主張に根拠を持たせることも有効です。
トラブル解決のゴールは、あなたが納得できる形で印刷物を得るか、適切な補償を受けることです。諦めずに、印刷会社と協力して最善の解決策を探しましょう。
④ 返品・交換の手順
再印刷や返金が決定した場合、不良品の返品や交換の手順について印刷会社からの指示に従います。
- 返品先と方法を確認:
- 不良品の返送先住所、返送方法(着払いか元払いか)、返送期限などを明確に確認します。通常、印刷会社の責任であれば着払いで対応してもらえます。
- 梱包方法についても指示がある場合はそれに従いましょう。
- 再印刷品の受け取り:
- 再印刷された印刷物が届いたら、すぐに再度品質を確認しましょう。同じ問題が繰り返されていないか、別の問題が発生していないかを丁寧にチェックすることが大切です。
- 返金の確認:
- 返金が行われた場合は、指定口座に正しく入金されたか確認しましょう。
このフローを最後まで丁寧に行うことで、一連のトラブル対応が完了します。もし再印刷品にも問題があったり、返金が滞ったりする場合は、再度速やかに印刷会社へ連絡し、状況を伝えましょう。
印刷トラブルを未然に防ぐためのチェックポイント
印刷物が届いてから不良が見つかるのは避けたいものです。トラブルが起きてしまった場合の対処法を知ることも大切ですが、何よりも未然に防ぐための対策を講じることが重要です。ここでは、データ作成から入稿、そして印刷前の確認段階で、あなたがチェックすべき重要なポイントを解説します。これらのポイントを押さえることで、印刷物の品質を高め、安心して納品を迎えられるでしょう。
データ作成時の注意点
印刷トラブルの多くは、実はデータ作成時のミスに起因しています。入稿データに不備があると、印刷会社側で修正作業が発生したり、意図しない仕上がりになったりする原因となります。以下の点に注意してデータを作成しましょう。
- カラーモードはCMYKで作成する:
- Webサイトやデジタル画面で見る画像はRGBカラーですが、印刷物はCMYKカラーで表現されます。RGBで作成されたデータをそのまま入稿すると、印刷時にCMYKに自動変換され、色味が大きく変わってしまうことがあります。特に鮮やかな青や緑、蛍光色などはくすんだ色になりがちです。
- デザインソフト(Illustrator、Photoshopなど)でデータを作成する際は、必ずCMYKカラーモードで設定しましょう。
- 画像解像度を適切に設定する:
- 印刷に必要な画像の解像度は、一般的に300~350dpi(dots per inch)が推奨されます。Web用の画像(72dpiなど)をそのまま印刷すると、画像が荒くぼやけてしまいます。
- 使用する画像は、原寸大で300~350dpi以上のものを用意しましょう。
- 画像を拡大しすぎると解像度が不足するため、注意が必要です。
- 塗り足し(裁ち落とし)を設定する:
- 印刷物を断裁する際、わずかなズレが生じることがあります。このズレによって、デザインの端に紙の地色(白)が見えてしまわないように、仕上がりサイズよりも外側まで色や画像を伸ばしておく領域を「塗り足し(裁ち落とし)」と呼びます。
- 通常、仕上がりサイズから上下左右に3mm程度の塗り足しを設定することが推奨されます。印刷会社の指定を確認し、必ず設定しましょう。
- 文字のアウトライン化を忘れずに:
- デザインデータに使用したフォントが印刷会社の環境にない場合、別のフォントに置き換わってしまったり、文字化けしたりする「文字化け」トラブルが発生します。
- これを防ぐには、使用している全ての文字を「アウトライン化」する必要があります。アウトライン化すると文字が図形として扱われるため、フォント情報に依存しなくなります。
- アウトライン化する前に、誤字脱字がないか最終確認を徹底しましょう。
- リンク切れに注意する(埋め込み/収集):
- Illustratorなどで画像を「リンク配置」している場合、入稿時にその画像ファイルを添付し忘れると、印刷時に画像が表示されません。
- 画像を「埋め込み」にするか、全てのリンク画像を収集して入稿データと一緒に送るようにしましょう。
これらのデータ作成時のルールは、印刷会社のウェブサイトにある「データ入稿ガイド」などに詳しく記載されています。必ず目を通し、指示に従ってデータを作成しましょう。
入稿前の最終確認
データ作成が完了したら、入稿する前に必ず最終確認を行いましょう。セルフチェックを徹底することで、多くのミスを防ぐことができます。
- 印刷会社のテンプレートを使用する:
- 多くの印刷会社が、正確なサイズや塗り足し、トンボなどが設定されたテンプレートを提供しています。これを利用することで、サイズ間違いや断裁ズレのリスクを減らせます。
- PDF/X-1a形式での入稿:
- PDF/X-1aは、印刷用のデータ交換を目的としたPDFの規格です。フォントの埋め込み、画像の解像度、カラープロファイルなどが適切に処理されるため、印刷トラブルを大幅に減らすことができます。
- 対応している印刷会社であれば、この形式での入稿を強く推奨します。
- データチェックサービスを活用する:
- オンライン印刷会社の中には、入稿データの不備を自動でチェックしてくれるサービスを提供しているところもあります。入稿前にこのサービスを利用することで、人為的なミスを発見しやすくなります。
- 見本となるPDFやJPGを添付する:
- 印刷会社にデータを入稿する際、完成イメージがわかるPDFやJPGなどの見本ファイルを一緒に添付しましょう。万が一、データ変換の際に文字化けやレイアウト崩れが起こっても、見本があれば印刷会社が気づきやすくなります。
- 最終的な目視チェック:
- 入稿する直前に、PDFデータなどを開いて、誤字脱字がないか、画像が正しく配置されているか、塗り足しが確保されているか、文字が切れていないかなど、隅々まで目視で確認しましょう。可能であれば、複数人でチェックするとより確実です。
- 特に、電話番号やURL、日付などの重要な情報は、ダブルチェックを徹底してください。
これらの確認を怠ると、修正費用や再印刷の手間、納期遅延など、予期せぬコストや問題が発生する可能性があります。
色校正の重要性
「画面で見た色と印刷物の色が違う」というトラブルは非常に多く、これはデータ作成の問題だけでなく、モニターの表示と印刷機の色の再現方式の違いから生じます。この問題を防ぐために有効なのが「色校正」です。
- 色校正とは:
- 本番の印刷に入る前に、実際に使用する紙やインク、印刷機で試し刷りを行い、色の仕上がりを確認する工程です。
- デジタル校正(PDF校正など)では画面上での色味確認となり、簡易的な確認にはなりますが、実際の印刷の色とは異なります。最も正確なのは、本機校正(本番と同じ環境で刷る校正)や平台校正(本番と同等の環境で刷る校正)です。
- 色校正で確認できること:
- 実際の印刷色味と、データの整合性。
- 文字の読みにくさや、細かいデザインの再現性。
- 紙とインクの相性。
- 色校正の費用と納期:
- 色校正は別途費用がかかり、その分納期も延びます。特に本機校正は高価ですが、大量部数の印刷物や、色味の厳密な再現が求められる印刷物(企業ロゴや製品パッケージなど)では、必ず行うべき投資です。
- 費用や納期とのバランスを考慮し、必要に応じて簡易的な色校正(DDCP校正など)を選択することも可能です。
色校正は、印刷後の「思っていたのと違う」という後悔をなくすための、非常に有効な手段です。特に初めての印刷物や、色にこだわりたい場合は、費用を惜しまずに検討することをおすすめします。印刷会社とのコミュニケーションを密に取り、これらのチェックポイントを確実に実行することで、安心して理想の印刷物を手に入れられるでしょう。
よくある質問(FAQ)
届いたものが不良品だと思うので、良品に交換(または返金)してほしい
まずは、記事内の「印刷物の不備・不良の種類を確認しよう」を参考に、届いた印刷物がどの種類の不良に該当するかを確認し、不良箇所を具体的に写真や動画で記録しましょう。その上で、印刷会社のウェブサイトにある「ご利用ガイド」や「免責事項」「品質基準」を確認し、不良と判断される範疇にあるかを確認してください。その後、速やかに印刷会社へ連絡し、状況を説明の上、再印刷や返金といった対応について交渉しましょう。多くの印刷会社では、商品到着後7日以内などの連絡期限を設けていますので、早めの対応が肝心です。
印刷会社でトラブルがあったらどうすればいいですか?
印刷トラブルが発生した場合、まずは落ち着いて状況を正確に把握することが重要です。具体的には、どの部分にどのような問題があるのかを特定し、写真などの客観的な証拠を記録してください。次に、印刷会社のカスタマーサポートや問い合わせ窓口に、具体的な状況と希望する対応(再印刷、返金など)を伝えます。連絡の際は、注文番号や氏名、連絡先を忘れずに伝えましょう。印刷会社とのやり取りは、常に冷静かつ丁寧に行うことが円滑な解決につながります。
印刷のクレームを防ぐには?
印刷物のクレームを未然に防ぐためには、データ作成時から入稿、そして印刷前の確認に至るまで、いくつかの重要なチェックポイントがあります。データ作成時は、カラーモードをCMYKに設定し、適切な画像解像度、塗り足し、文字のアウトライン化を徹底しましょう。入稿前には、印刷会社のテンプレート使用、PDF/X-1a形式での入稿、見本となるPDFの添付、そして何よりも最終的な目視チェックを複数人で行うことが推奨されます。特に、色味にこだわりたい場合は、本機校正などの色校正を依頼することが非常に有効です。
増刷と再注文の違いとは?
増刷とは、以前に注文した印刷物と「全く同じ内容・仕様」で、追加で印刷することを指します。データや仕様の変更がないため、比較的スムーズに手配でき、費用も抑えられる場合があります。一方、再注文とは、以前の印刷物と「異なる内容や仕様」で新たに印刷を依頼することです。例えば、デザインの一部変更、用紙の変更、部数の変更などがある場合は再注文となります。再注文の場合は、新たにデータチェックや印刷工程が始まるため、増刷よりも時間や費用がかかる傾向があります。印刷会社に問い合わせる際は、どちらに該当するかを明確に伝えましょう。
まとめ
本記事では、届いた印刷物に不備が見つかった際の具体的な対処法から、トラブルを未然に防ぐためのポイントまでを詳しく解説しました。
重要な要点を振り返りましょう。
- まずは落ち着いて、不良の種類を正確に把握し、写真や動画などで明確に記録することが対応の第一歩です。
- 印刷会社への連絡はできるだけ早く行い、詳細な状況説明と、場合によっては現物の提出を求められることがあります。
- 再印刷や返金などの対応交渉では、各印刷会社の品質基準や免責事項を理解した上で、冷静かつ丁寧に話し合いを進めましょう。
- そして何より、今後のトラブルを防ぐためには、データ作成時の注意点(CMYK、解像度、塗り足し、アウトライン化など)や、入稿前の最終確認、色校正の活用が不可欠です。
印刷物のトラブルは誰にでも起こり得ますが、適切な知識と準備があれば、慌てることなく、冷静に対応し、理想の仕上がりを追求できます。今回得た知識を活かし、次回の印刷からは自信を持って進行してください。
もし再び印刷物の不備に直面した際は、この記事があなたの強い味方となるでしょう。諦めずに、納得のいく解決を目指しましょう!

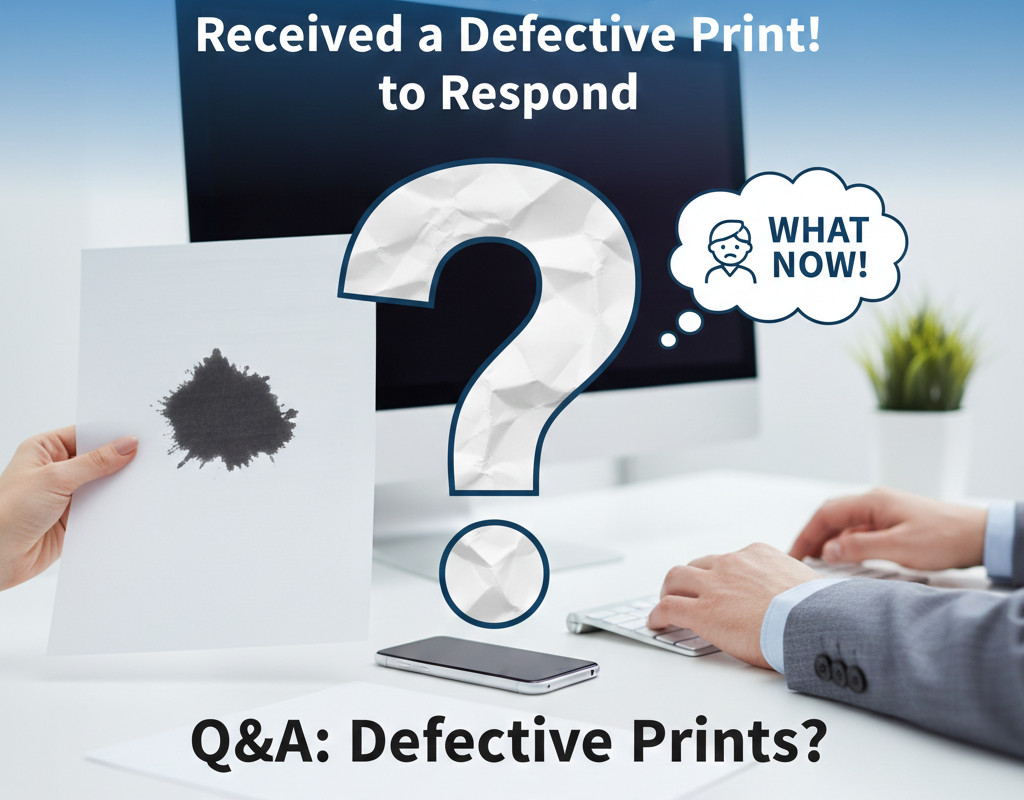




コメント